1週間がんばって働いて、週末はマッサージや整体で身体のメンテナンスをするという人、
少なくないと思います。
年齢とともに疲れやすくなり、しかも、放置しておくと次々と疲れが積み重なるようになります。
「私は若いから大丈夫。体力があるから大丈夫」と思っていても、
やがて「メンテナンス重要!」という日がきますので、油断なさらずに。
ちなみに、メンテナンスは身体を元の状態に戻すことを指し、
身体の状態を向上させることはコンディショニングと言うそうです。
ご存知でしたか?
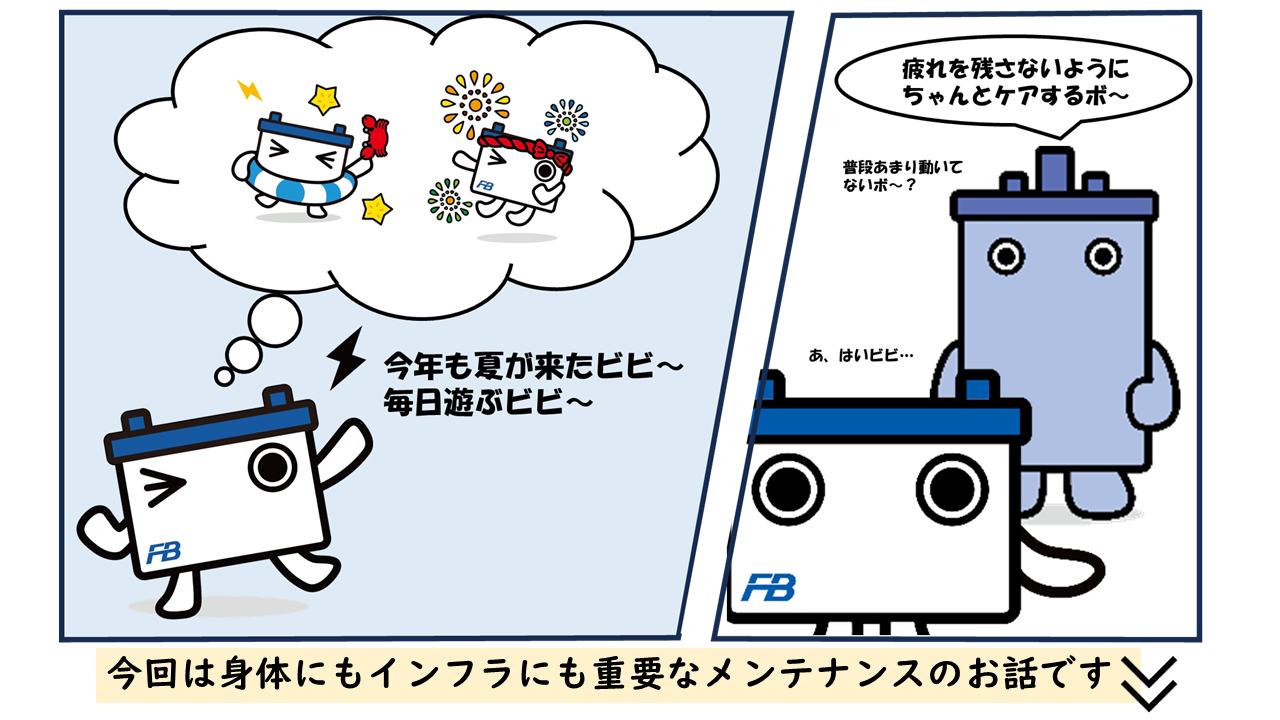
そう、今回のテーマはメンテナンスです!
身体のメンテナンスに関する話題はここまでにし、
ここからは日本中のインフラメンテナンスの話へ。
そもそも、日本のインフラの多くは、
高度経済成長期(1955年頃〜1973年頃)に整備されました。
そこから50年以上経って老朽化が進んでいます。
しかも、地震・津波、火山の噴火、豪雨が起きれば、
老朽化が早まるのは当然です。
2012年(平成24年)の笹子トンネル天井板落下事故を覚えていますでしょうか?
これをきっかけに、国土交通省では翌年を「社会資本メンテナンス元年」とし、
インフラ長寿命化に向けて、さまざまな取り組みを開始。
不具合が生じてから修繕する「事後保全」から、
不具合が生じる前に修繕を行う「予防保全」へと転換することになりました。
メンテナンス人材も予算も不足している地方の市町村に対しては、国が技術支援を実施。
メンテナンスサイクルの情報蓄積や共有化を図り、
点検・補修に役立つロボットやセンサーなどの新技術開発への新規参入を促進。
それらを活用してもらうための仕組みも構築しました。
「事後保全」から「予防保全」に転換すると、
10年で25%、30年で47%※も維持管理・更新費が減少する
とされているので、コスト面でも効果的ということがわかっています。
また、笹子の事故から2年後には、道路法も改正され、
橋やトンネルの点検は遠望目視が中心だったところ、
5年に1度の近接目視による点検が義務付けされました。
こうやって国レベルで膨大な知識やデータを蓄積し、
民間企業や研究機関は先端技術をどんどん開発することで、
行く行くはインフラメンテナンス自体を世界に輸出することも目指しているそうです。
そんな夢のある話を実現するには、まずは日々のメンテナンスから!
古河電池としては、蓄電池をいつでも万全の状態で使用してほしいと考えます。
蓄電池は交換時期を過ぎても外観はあまり変わりませんが、性能は確実に落ちてしまいます。
交換時期を過ぎた蓄電池を使い続けた場合、非常時に非常照明が点灯しない、
非常用自家発電設備が始動しないなどで、
例えば、地下街や夜間の公共施設からの避難が困難になってしまい、
人命にかかわる事故に繋がることも考えられます。
また、温度の高いところやほこりっぽい場所に長期間設置しておくと故障の原因になるので、
周辺環境にも気を配り、決められた頻度で蓄電池の点検や充電装置の部品の交換をしましょう。
メンテナンスが楽な制御弁式鉛蓄電池を選ぶのもおすすめです。
メンテナンスの点検結果によっては、交換時期の前であっても、
予防保全として蓄電池や充電装置の更新を計画的に実施しましょう。
他にも蓄電池のことで知りたいことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
※ 経済財政運営と改革の基本方針2018 第3章「経済・財政一体改革」の推進
▼お問い合わせはこちら
fb-indst.sales@furukawabattery.co.jp
古河電池株式会社 産業機器営業統括部 営業技術部







